タイムパフォーマンスのこと。時間対効果のこと。Z世代から急速に広がった。
Z世代から急速に広がった?
タイパは端的に言ってしまうと、膨大な数の動画を2倍の速さで見るということ。
タイパは、Z世代よりも前に考えていた人がいる。
岩井康介という大学生が、1990年に「2倍速テープ学習法」という本を出している。
今から30年前ですよ。この大学生も今は50代のおっさんになっているだろう。
内容は、教科書や参考書を音読したものを録音してそれを2倍の速さで再生するということ。
当時は動画を再生するのはビデオデッキで、ビデオテープを録画再生するのはビデオカメラがあったが高額で庶民は手が出しにくかった。
データ通信の事情も、NTTの電話回線を使ったキャプテンシステムというインターネットの先駆けのようなものはあったが、まだ文字情報だけのやり取りだった。
NTTの電話回線を使うために使えば使うほど電話代がかかってしまった
「2倍速テープ学習法」は現代風に当てはめれば音声のみのタイパという感じ。
1990年頃に流行らなかったのは、なぜだろう?
1990年頃にこの本が流行らなかった原因は何だろう?
まず、この本は受験参考書のコーナーにあった。
受験参考書コーナーは、ほぼ受験生しか見に行かない。あとは学校の先生?
邪道な考えを嫌う受験生や先生が多かったために普及しなかった
当時は、金ぴか先生という代々木ゼミナールで英語を、例の方法という著書で一世を風靡した有坂誠人という代々木ゼミナールで国語を、グリデン式古文という著書で有名だった和角仁という予備校の先生が、試験で点数を取るためだけの邪道なテクニックを教えていた。
受験生には好評だったが、学校の先生などを含む同業者のウケは悪かった。
それらの先生の出した本は、書店では色物扱いで陳列されていたが、「2倍速テープ学習法」もそのたぐいの扱いだった。
私は、当時は受験テクニックのような本が好きだったので、藁にも縋る思いで読んでいたと思う。
アナログの限界?
私は、「2倍速テープ学習法」をすごい本だと思ったが、これを実行するのには非常に手間がかかるので挫折した。
やり方は、教科書や参考書を読んでテープに録音して、カセットデッキの倍速機能を使い倍速再生するということだが、教科書をきちんと読むのは意外と難しい。絶対につっかえる。
読めない漢字は録音をストップして辞書で調べる。これも手間がかかる。
現在のようなネット社会ではなかったので、全部自力で解決しなければいけなかった。
カセットテープを録音しているときに一時停止をするわけだが、この一時停止時の雑音も録音されてしまう。
この作業をしているときに、母親が部屋に来てギャーギャー言われると、中断される上にギャーギャー声まで録音されてしまう。
このようなアナログなやり方なので、作業がしんどかった。
吹き込んだだけで疲れてしまう、というか勉強した気分になってしまう。
録音するためにはカセットテープが何本も必要になる。
それを何本も再生しなければいけない。しかも自分の声。
つっかえた個所、勝手に録音された雑音などを聞くとテンションが下がる。
知り合いに声優がいたらとか、声優になろうかと思ったことも。
当時のAV機器
1990年頃はカセットテープを再生するAV機器といえば、ラジカセやウォークマン、アイワのカセットボーイなど、当時のウォークマンは持ち運び用に開発されたが、やっぱり大きかった。
当時のカセットテープは、再生するたびにテープが擦り切れるので何度も聞くと音が劣化する。
そのために、まず保存用のカセットテープを作り、何度も聴く用のテープにダビングした。
船橋駅近くのショッカーや長崎屋Big-Offで安くて音がいいカセットテープをたくさん買ったなあ。
今は、パソコンである程度簡単にできてしまう
今は、簡単なテキストは音声認識で文字化できて、その文字は音声ファイル化でき、音声もボーカロイドが流行したおかげで無料でもそこそこきれいな声優の声を選べる。
音声化するときに誤読されることもあるが、それは文字登録しておけばいい。
作った音声ファイルは、オンラインコンバーターで2倍以上のスピードに変換できる。
変換した音声ファイルの拡張子が.wavだったら、オンラインコンバーターなどで、.mp3の拡張子に変えるだけ。
変換した音声ファイルはデジタルオーディオプレーヤーに送って何度も再生できる。
デジタルオーディオプレーヤーはUSBメモリと同じくらいの大きさ、カセットテープ式のウォークマンと比べたら持ち運びしやすい。なくしやすいというデメリットもある。
ただ、、安いものは1000円位からあるので、音声ファイルデータをバックアップしておけば、なくすリスクを防げると思う。
デジタルオーディオプレーヤーで何度再生してもカセットテープのように音が劣化しない。音声ファイル自体が小さいので、場所をとることはない。
すごい時代になったものだ。
タイパという言葉は、Z世代が造った用語?だが、
タイパという言葉は、Z世代が造った用語?だが、
仕組み自体は30年前には実践している人がいたので、真新しいことではないということ。
だから、おっさんが何か新しいことを知る必要に迫られたときにこのやり方は使えるはず。

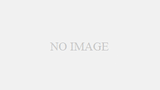
コメント